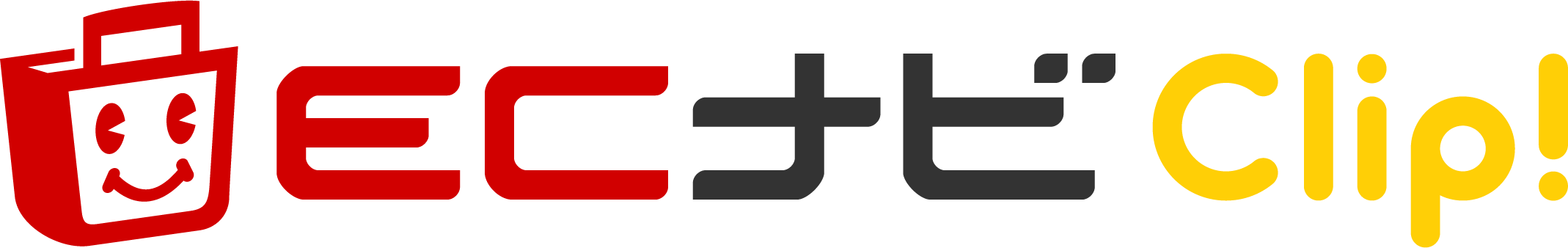「夏になってから、愛犬の元気がない」「散歩を嫌がるようになってしまった」などの症状がある場合、愛犬が夏バテを起こしている可能性があります。夏バテを起こすと、愛犬の体力が徐々に落ちていき元気や食欲がなくなるだけでなく、熱中症を引き起こすリスクもあります。また、体力や免疫力が落ちることから、風邪や病気にかかりやすくなってしまうことも。
大事な家族のためにも、夏バテ対策をしっかりしておきたいですよね。そこでこの記事では、犬が夏バテを起こす原因や対策、予防法について詳しく解説します。夏バテしやすい犬種や、夏バテしてしまったときにおすすめの食事・食材についても紹介。
とくに食材についてはどのご家庭にもあるもの、スーパーで簡単に手に入るものを中心に紹介しているので参考になるはずです。愛犬が夏バテしてお困りの方はぜひ参考にしてください。
- 犬の夏バテ症状は季節の変わり目から徐々に現れる
- 熱中症は健康な犬でも急に発症する可能性があるので注意
- 夏バテ対策にはウェットフードを凍らせたり、犬用スポーツドリンクを与えたりして水分補給を徹底するのが大切
applica編集部がおすすめするドッグフード2選
まずは、applica 編集部がおすすめするドライフードとウェットフードをご紹介します。「このこのごはん」は低カロリーで小型犬も食べやすいドライフード。「ブッチ」はウェットフードの中でも特に食いつきが期待できる、全犬種におすすめのフードです。
| 【ドライフード】 | 【ウェットフード】 |
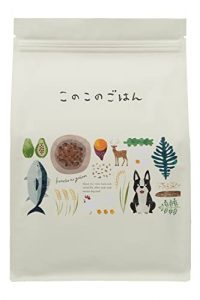 |
 |
| このこのごはん | ブッチ |
| 3,850円 (税込) |
1,650円 (税込) |
|
動物性たんぱく質がたっぷりで低脂肪。粒の大きさが直径約7〜8mmと小さめなので、小型犬の食いつきの良さが特徴。 |
肉類が最大92%を占めている高たんぱくなフード。生肉のように水分量が豊富なため、胃腸の弱いワンちゃんも消化吸収しやすい。 |
少しでも気になった方は、ぜひ公式サイトより詳細をご確認ください。
※記事内の商品と一部重複している場合がありますが、ご了承ください。
犬が夏バテしたときの症状

犬が夏バテすると、具体的には次のような症状が見られます。
元気がなくなる
春頃に比べ、犬の元気がなくなってしまったら夏バテかもしれません。具体的には次のような兆候がないか確認しましょう。
-
ぐったりしてなかなか動こうとしない
-
寝ていることが多くなる
-
動きがのろのろとしている
-
おもちゃを見せても遊ぼうとしない
夏バテした犬は元気がなくなり、おもちゃで遊ぼうという気力もなくなることが多いです。動くのがおっくうになり、寝ていることが多くなります。仮に動いてものろのろとしており、機敏な動きではないことも。春や冬など、ほかの季節と違う様子であれば夏バテを疑ってみましょう。
食欲不振
食欲がなくなるのも夏バテの症状の1つです。元気はあるのに好物を与えてもあまり食べなかったり、おやつだけ食べて主食を残したりといったことがないか確認しましょう。夏バテが進むと消化器官も弱り、下痢を起こすこともあります。
そのまま放置していると食べないことから免疫力も落ち、病気にかかりやすくなることもあるので食欲を維持するようにすることが大切です。
散歩を嫌がる
散歩を嫌がったり、すぐ地面に寝そべったりするのも夏バテ症状の1つです。犬は、人間よりも物理的に暑さを感じやすい環境にいます。
たとえば夏はアスファルトの地面が非常に高温になります。アスファルトは黒っぽい色をしているので熱を吸収しやすく、最高で60℃を超えることも。歩いただけで肉球がやけどをしてしまうこともあるほどです。また、単純に地面と近い位置に体があるため、人間より地面の熱気を体全体で感じやすくなります。
もし、途中で犬の呼吸が荒くなったり動きが緩慢になったり、苦しそうな様子を見せるようならただちに散歩を中止してください。また、ふらついていたら肉球を火傷している可能性もあるので確認しましょう。
嘔吐・血便などの症状がある
夏バテの症状が重くなると、嘔吐や血便の症状を引き起こすこともあります。これは、暑さにより消化器官が弱り消化不良を起こしたり、食事をとる量が減って免疫力が下がったりすることがおもな原因です。
また、よだれを垂らしたり呼吸が荒くなったりといった症状もある場合は熱中症の危険もあります。病院に行けば冷却や輸液による水分補給など処置をしてもらえるので、できるだけ早めに病院に行きましょう。
夏バテと熱中症の違い
夏バテと熱中症の違いで一番わかりやすいのは発症までの時間です。夏バテは夏の気温変化により、徐々に体調を崩すことを指します。一方、熱中症は突然やってくるもので、弱っている犬だけでなく元気いっぱいの犬でも条件が重なれば発症する可能性があります。
人間の場合はまれに「夏場、車内に子供を置き去りにしたために、子供が熱中症になり死亡する」といった痛ましいニュースが聞こえてくることもありますが、犬も同じです。健康な犬でも暑く閉め切った部屋や、涼むことのできない屋外にいれば数十分で簡単に熱中症になってしまいます。実際犬の熱中症の原因としては、「車内での放置」が非常に多いです。
熱中症の症状は夏バテよりもさらにひどく、たとえば次のような症状が見られます。
-
呼吸が荒く、よだれを垂らす
-
意識がなく、呼んでも反応しない
-
肉球が白い
-
水を飲まない
-
ぐったりとして動かない(動けない)
熱中症は発症から数時間で命を落とすこともあります。熱中症の兆候があったら様子を見るのではなく、首やわき、後ろ足の付け根など太い血管の通る部分を氷や濡れタオルなどで冷やしながら一刻も早く病院へかかることが大切です。
犬が夏バテする原因

いったい犬はなぜ夏バテをしてしまうのでしょうか。夏バテの原因には、次のように犬の身体構造や温度差が関係しています。
発汗器官が発達しておらず暑さに弱い
犬はもともと暑さに弱いことで知られています。犬は全身が毛に覆われており、人間のように汗をかくための発汗器官が発達していません。犬が汗をかくのは肉球の裏や鼻先といったわずかな部分しかなく、表面積が少ない分発汗効率も悪いです。通常、犬は汗をかけない代わり、口で呼吸をして体内の熱を逃がし、体温を調節しています。
人間のように汗による体温調節ができないため、人間より暑さに弱いです。なお、猫も犬と同様に肉球や鼻先などにしか発汗器官がありませんが、猫はもともと砂漠起源の生き物なので犬よりは暑さに強いとされています。もし猫と一緒に飼っている場合、猫に合わせて室温を調整していると犬がバテてしまう可能性があるので注意してください。
温度差で自律神経が乱れる
夏バテは季節の境目に温度差が原因で自律神経が乱れ、症状があらわれることが多いです。
たとえば、飼い主さんの中には3月には長袖の服の上にコートを着ていたのに、4月には半袖の服を着るようになったという人もいるのではないでしょうか。4月頃から急激に温かくなりはじめ、また朝晩の寒暖差も大きくなるため犬が自律神経を乱しやすくなります。また、散歩で暑い屋外と涼しい室内を行き来するのも原因の1つです。
このように、4~5月からひっそりと犬が体調を崩す要素が積み重なっていき、梅雨を迎える6月頃から9月頃にかけてピークを迎えます。徐々に夏バテの症状が見えるようになるので、よく体調管理してあげましょう。
暑さに弱い犬種の例

犬種によっても体格や毛の種類が異なるので、夏バテのしやすさが変わってきます。特に注意したい、夏バテしやすい犬種の例をご紹介します。
毛の密度が高い犬種
 柴犬 |
 チワワ |
 ポメラニアン |
柴犬や秋田犬、チワワやポメラニアンなど、毛の密度が高い犬は暑さに弱いことで知られています。毛が密集しているため毛の通気性がなく、こもった熱を逃がしにくいのが原因です。対策としてはブラッシングしてあげると毛の通気性がよくなり、熱が逃げやすくなるのでおすすめです。夏の間は毛を短くカットしてあげる手もあります。
鼻が短い犬種
 パグ |
 シーズー |
 ボストンテリア |
パグやフレンチブルドッグ、シーズー、ボストンテリアなどのいわゆる「鼻ぺちゃ顔」の犬も暑さに弱いです。このような犬は「短頭種」と呼ばれており、頭蓋骨の長さに比べて鼻の長さが短く、独特のバランスをしているのが特徴。骨格上呼吸がしづらく、体温調節が苦手な犬種です。短頭種は人間が品種改良を重ねたことで生まれた種類ともいわれています。
短頭種の犬は骨格上、ほかの犬(中頭種や長頭種)の犬より気管が狭かったり、鼻の孔が小さかったりします。同じ環境下にあってもほかの犬より呼吸が荒くなり、苦しそうにすることもあります。夏バテや熱中症のリスクも高くなるので、よく気づかってあげましょう。
寒冷地方起源の犬
 シベリアンハスキー |
 ゴールデンレトリバー |
 サモエド |
シベリアン・ハスキーやゴールデンレトリバー、サモエドなど、寒冷地方を起源とする犬も暑さに弱いです。このような犬は「ダブルコート」といって、寒さに耐えられるように二層に分かれた分厚い被毛を持っています。寒さには強いですが、夏には弱いので体調管理を念入りにしてあげてください。
ダブルコートの犬は換毛期があり、夏になると冬毛から夏毛に生えかわりますが、夏毛になっても温暖化が進み湿度も高い日本の夏には不向きです。
人間にたとえると、ダブルコートの犬が夏毛になるのは冬用のコートを脱いで長袖になるようなものです。半袖を着ている状態ほど涼しくはないので、暑さ対策を徹底しましょう。
子犬・老犬
 子犬 |
 シニア犬 |
子犬やシニア犬も暑さに弱いです。成犬に比べると暑さに耐えるだけの体力に乏しく、体温調節機能も働きにくいため、夏バテを起こしやすくなります。特に、子犬はもともと体温が高いこともありいっそう暑さに弱いです。
子犬や老犬は熱中症のリスクも高くなるので、水分補給や冷房など対策を万全にしておきましょう。老犬で移動するのがおっくうな状態の場合は、水や冷却ジェルマットなどを犬の近くに置いてあげるのもおすすめです。
ただし、子犬や老犬は自分で体温調節するのが苦手なので、冷房のききすぎで逆に体が冷えてしまうこともあります。こまめに様子を見て、寒がっているようなら温度を上げることも大切です。
犬が夏バテしたときの対処法

もし大事な愛犬が夏バテしてしまったのなら、次の方法で早めに対策し、体力を戻してあげましょう。
嗜好性が高めの食事を用意する
まずは元気のないときでも食べたくなるような、美味しい食事を用意してあげましょう。普段ドライフードをあげているのなら、犬用のふりかけやおやつ、缶詰などをトッピングしてあげると嗜好性が高くなり犬が喜んで食べてくれやすいです。また、ささみのゆで汁をかけると風味がよくなり、食いつきが増すだけでなく水分補給にも役立ちます。
それでもあまり食欲がわかないようであれば、手作りのごはんや市販の犬向けごちそうなどを与えるのもおすすめです。食べないと体力や免疫が落ちてしまうので、食事を工夫して毎日の給餌量をキープするようにしましょう。
犬の食いつきをアップする方法や、食いつきのよい食事についてはこちらの記事でも解説しているので参考にしてください。
 食いつきがよいドッグフードおすすめ16選|選び方・食いつきをよくする方法・注意点まで解説【獣医師監修】【PR】
食いつきがよいドッグフードおすすめ16選|選び方・食いつきをよくする方法・注意点まで解説【獣医師監修】【PR】
水分補給を徹底的に行う
夏バテや熱中症予防に重要なのは水分補給です。たっぷりと新鮮な水を用意し、自宅でも散歩中でも、いつでも飲めるようにしてあげましょう。夏場は水が傷みやすいので、1日最低2回は取り替えることが大切です。雑菌の繁殖や水温上昇を防ぐため、直射日光を避けて水の入った器を置きましょう。
また、水をあまり飲まないようなら普段の水に次のような工夫も取り入れてみましょう。
-
ヨーグルトの上澄みを混ぜる
-
氷を数個浮かべて水を冷やす
-
犬用のサプリやスポーツドリンクを混ぜる
ヨーグルトの上澄み(ホエー)を混ぜると嗜好性が上がり、犬が水に興味を持ってくれやすいです。氷が好きな犬であれば、氷を数個浮かべてあげると氷ごと飲んでくれるでしょう。
また、水にサプリやスポーツドリンクを加えると、カリウムやナトリウムなどミネラルの補給に役立ちます。ただし、人間用のスポーツドリンクを与える場合はキシリトールが入っていないか確認してください。キシリトールを犬に与えると中毒を引き起こすことがあり危険です。そのほかにレモンやグレープフルーツなど酸味の強いフレーバーのものも犬によっては苦手で、逆に体調を崩してしまうこともあります。
人間用のスポーツドリンク自体は与えても問題ありませんが、上記のように犬に害があることもあるのでできれば犬用のスポーツドリンクを用意しておくと安心です。
食事を分ける
犬が夏バテして食欲がないときは、食事の回数を増やし、少しずつ分けて与えるとよいです。少量ずつなら食欲がなくても食べやすくなります。成犬の食事は1日2回が基本ですが、子犬のときのように1日3~4回にしてみましょう。
また、子犬や老犬で1回の食事を食べきれない場合は、さらに回数を増やしてみるのもおすすめです。
なお、回数を増やす場合は犬の体に負担がかからないよう、食事の間隔をできるだけ均等にしてあげてください。
散歩コースや時間帯を変える
犬が散歩を嫌がるときや、夏バテの予防をしたいときは散歩のルートや時間帯を変えてみましょう。たとえば、次のような工夫が有効です。
-
アスファルトの道を避けて土の多い公園周辺をメインのルートにする
-
日陰を歩かせる
-
早朝や夕方など、涼しい時間帯に散歩する
特にアスファルトは熱で肉球を火傷させてしまうリスクもあるため避けるのが無難です。しかし、自宅の前の道路などやむを得ず歩く場合は、飼い主さんがアスファルトを触ってみて温度を確認してから歩かせるようにしましょう。
市販されている、夏向けの冷感ウェアを着せてあげるのも有効です。
夏バテを防ぐおすすめの食事

体力をつけ、夏バテを撃退するためには食事が重要です。夏バテして食欲が落ちているときでも食べやすい、おすすめの食事や食材をご紹介します。
ウェットフード
飼い主さんが手軽に用意できる夏バテ対策の食事といえばウェットフードです。一般的なドライフードは水分の含有量が10%ほどですが、ウェットフードの場合は約80%が水分でできています。ウェットフードを食べるだけでかなり水分補給ができる上、嗜好性が高いのでおすすめです。
ただし、ほとんど水分であることから、カロリーはドライフードに比べてかなり低めなのであくまでおやつやトッピングなど、補助的に利用しましょう。
愛犬が喜ぶウェットフードや選び方、与えるときの注意点などについては、こちらの記事でも解説しているのでぜひお読みください。
 ウェットタイプのドッグフードおすすめ14選|選び方や与える際のポイントも解説【PR】
ウェットタイプのドッグフードおすすめ14選|選び方や与える際のポイントも解説【PR】
「ブッチ」で犬が喜ぶシャーベットを作ろう
ウェットフード選びに悩んだら、そのまま食べさせることもアレンジすることもできる「ブッチ」を試してみるのがおすすめです。
「ブッチ」は全年齢・全犬種対応の無添加フードなので、成犬はもちろん子犬や老犬にもぴったり。栄養価や水分の含有量は本物の生肉を参考にして作られているので、夏バテしているときでも犬の食欲を刺激してくれます。チキン味とチキン&フィッシュ味、ビーフ&チキン&ラム味の3種類があるので、愛犬の好みに合わせて選べるのも魅力です。
また、ブッチは冷凍保存にも対応しているので、犬が大好きなシャーベットも作れます。普段はもちろん、お散歩中のおやつとしても最適です。
ブッチが気になる方は、こちらの記事もご覧ください。
 【2024年5月最新】ブッチドックフードのリアルな口コミ・評判|愛犬の食いつきぶりと保存方法を紹介【PR】
【2024年5月最新】ブッチドックフードのリアルな口コミ・評判|愛犬の食いつきぶりと保存方法を紹介【PR】
「PETOKOTOFOODS」は食欲がないときにおすすめ
フレッシュフードの「PETOKOTOFOODS」は、食いつきが抜群なので食欲のない犬におすすめです。
犬の栄養学に詳しい獣医師がレシピを開発し、ヒューマングレードの国産材料を使用しているのが特徴。国内で調理後すぐ冷凍しているので美味しさがキープされ、いつでも新鮮な食事を与えられます。
フレッシュフードなので、手作りのごはんのような見た目で愛犬の食欲を刺激します。公式サイトからの購入なら、食べなかったときの全額返金保証や獣医師による健康相談などのサービスを受けられるのも魅力です。
PETOKOTOFOODSが気になる方は、こちらの記事をご覧ください。
 PETOKOTOFOODS(ペトコトフーズ) の口コミ評判|値段や食いつきのよさを徹底レビュー【PR】
PETOKOTOFOODS(ペトコトフーズ) の口コミ評判|値段や食いつきのよさを徹底レビュー【PR】
体を冷やす食材
普段の食事に、体を冷やす食材や水分が多い食材を与えると体温を下げてくれるのでおすすめです。家庭で簡単に手に入る夏バテ向きの食材にはたとえば、きゅうり、トマト、スイカ、ズッキーニなどがあります。
| 食材 | 特徴 | 与え方・注意点 |
|---|---|---|
きゅうり |
・水分が豊富なので水分補給に最適 ・噛みごたえがあるので犬が喜びやすい |
・まるごと生で与えてOK ・消化能力が落ちているときは皮を取り除く |
|
トマト
|
・水分が豊富なので水分補給に最適 ・リコピンやβカロテンなど、抗酸化作用のある成分が豊富 |
・へたを取ってから与える ・小さく切って与えると食べやすい ・青くなく、完熟したものを与える |
|
スイカ
|
・水分が豊富なので水分補給に最適 ・カリウムやビタミンなど健康維持に役立つ成分が豊富 |
・そのまま果肉をおやつとして与える ・砕いて食事に混ぜる ・種や皮は消化しにくいので与えないこと |
|
梨
|
・水分が豊富なので水分補給に最適 ・食物繊維が豊富 |
・そのまま果肉をおやつとして与える ・皮や芯、種は取り除く ・やや消化しにくいので少量ずつ切って与える |
|
ズッキーニ
|
・カリウムやビタミンCが豊富 ・犬の体を冷やしてくれる食材 |
・生でも茹でても与えられる ・そのまま皮ごと与えてOK |
|
オクラ
|
・ミネラルが豊富 ・犬の体を冷やしてくれる食材 |
・ヘタをとり刻んで与える(種は与えてOK) ・普段の食事のトッピングとして混ぜる |
また、上記の食材を与えるときは共通の注意点として少量から与えましょう。犬の中には食材にアレルギーを持つ場合もあります。いきなり大量に与えるとアレルギーを起こしたり、アレルギーがなくても下痢や嘔吐などを引き起こしたりすることも。必ず少量から始め、様子を見てから量を増やしましょう。
犬の簡単な夏バテ予防法4選

もしまだ夏バテの兆候は見られないものの、念のため対策しておきたいのであれば次の方法を取り入れてみましょう。
冷房をつける
室内犬の場合、冷房はできればつけっぱなしにして、常時快適な室温を維持しましょう。犬種や年齢などにも左右されますが、室温22~26℃になるように冷房設定するのがおすすめです。ダブルコートの犬のように暑さに弱い場合は、室温19~23℃とやや低めに設定してあげましょう。
なお、扇風機で代用したい方もいるかもしれませんが、扇風機はあくまで空気を循環させるだけで室温を下げる効果はありません。必ず冷房と併用するようにしてください。
水や食事はこまめに交換する
夏は水や食事が腐りやすいので、いつでも新鮮なものを口にできるようこまめに交換しましょう。水は最低でも1日2回交換を目安にし、5回、6回など交換回数が多い分には問題ありません。
フードに関しては食べたらすぐ器を片づけ、出しっぱなしにしないことも大切です。
また、水やフードの容器はその都度しっかり洗ってください。洗剤を使う必要はありません。菌が心配な場合は洗剤よりも煮沸消毒が有効です。
ブラッシングをこまめに行う
シングルコート・ダブルコートなど被毛の種類に関わらず、ブラッシングをこまめにしてあげましょう。ブラッシングすることで余分な毛が抜け落ち、毛の通気性がよくなるため熱がこもりにくくなります。
夏バテ対策グッズを利用する
ペットショップや通販などで、犬用の夏バテ対策グッズを購入しましょう。犬用のクールマットや保冷ウェア、アイスノンなどがあると便利です。また、水分補給がしやすくなるよう、循環式の給水器を設置するのもおすすめ。
あるいは、厳密にはグッズではありませんが家庭用のプールを用意して水浴びさせたり、ホースで水遊びさせたりする方法もあります。
まとめ
この記事では、犬が夏バテする原因や対策、予防法について紹介してきました。また、犬におすすめのウェットフードも紹介しているので、もし、今回紹介した商品の中で魅力に感じたフードがあれば、ぜひこの機会に購入を検討してみてはいかがでしょうか。

※この記事は2023年2月6日に調査・ライティングをした記事です。
※本記事の価格はすべて税込で表記しています。